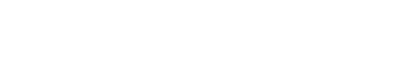『文庫X』仕掛け人 新人女性作家の挑戦作。自分ならここを売り出す
本のプロが読む、額賀澪『拝啓、本が売れません』(「さわや書店」長江貴士さん)
翻って、本書はどうか。
本書の著者である額賀澪の本職は小説家だ。新人賞を二作受賞し、新人作家としては非常に恵まれた(と編集者に言われるという。主に初版部数などについての話だ)作家生活をしているのだが、しかし大きな危機感を常に抱いている。著者は自らを「平成生まれの糞ゆとり作家」と称していて、ゆとりだからこそ現状に安心しないし、「大丈夫」という言葉に危機感を抱くのだと語る。
確かに今はまだ恵まれた環境にいるかもしれない。でも、初版部数は実際に減っている。書店に行っても、「文芸書(小説の単行本)」の売り場はどんどん狭くなっている。業界全体から元気が感じられないような気がする。著者は、お金や地位や世間的な幸せみたいなものにさほど重きを置いていない(どうでもいいけど、僕も同じです)。とりあえず、死ぬまで小説を書いて生きていければ本望だと考えている。しかし、そういう低いハードルさえ、もしかしたら望めない時代がやってくるかもしれない。
だから著者は、「本が売れない!」「ヤバい!」と、「本」というメディアの中で繰り返し語る。
それだけなら、前述のお笑い芸人の指摘と近いものに感じられるだろう。しかし本書の場合、ちょっと違う。
お笑い芸人の発言の根底には、「テレビが見られていないって言う『だけ』の行動に意味なんてない」という意識がある。そう、そんな風に危機感だけ煽って何も行動しないような振る舞いには、何の意味もないだろう。
しかし額賀澪は、「本が売れない!」という危機感からちゃんと行動に移す。彼女は「本」に対して「小説家」という役割で関わっている。しかし「本」は、「小説家」だけで生み出されているわけではない。今まで自分は「小説を書く」という部分でしか努力をしてこなかった。でもそれだけではきっと、この先行き詰まる。じゃあどうするべきかと考えて、著者は「本」に何らかの形で関わる様々な人間に会いに行き、「本を売る」ということについて意見を交わすのだ。
「本が売れない!」というのは、現状を打破するための自らへの叱咤であり、具体的な行動の道筋を掴むための建設的な自虐なのである。
額賀澪が辿る「本を売る」ための奮闘は、ある意味で非常に面白い結論に行き着くことになる。著者はそれをある有名な童話に喩えているが(一応ネタバレにならないように作品名は伏せる)、なるほどと思ってしまった。
著者は、スーパー編集者、webコンサルタント、映像プロデューサー、装丁家など様々な人間に会いに行く。もちろん書店員にも会いに行くのだが、その書店員とは実は、さわや書店の松本大介である。僕の上司だ。普段からギリギリ(アウト?)な攻めきった発言をする人だが、本書でもそのヤバさが存分に描き出されている。
額賀澪は彼らに、本(あるいは彼らが売っているモノ)を届けるために何をしているのかや、映像化や書店店頭での仕掛けに「選ばれる」要素は何か、など様々なことを聞き、その中で自分にも出来ることがないかを考えていく。確かに著者は「小説家」として良いモノを生み出さなければならないのだが、良いモノだからといって売れる時代ではない。だからその良さを届けるために何が出来るのかを考えなければならない。額賀澪の奮闘は、本に限らず、【モノを生み出すこと】【モノを届けること】に関わるすべての人に関係してくるものだと思う。